酒井 清治 名誉教授

「考古学が趣味」と語る酒井清治名誉教授は駒澤大学で遺跡発掘の基礎力を磨いたことに誇りを持ち、遺物を「観る」ことを大切にいくつもの新説を発表し、考古学に貢献してきた。
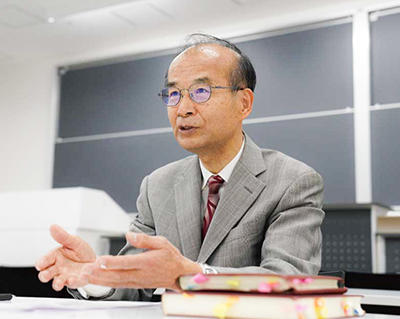
酒井清治名誉教授は、日本の古墳時代から平安時代にかけて盛んに作られた陶質土器「須恵器(すえき)」と「瓦」、古代寺院、渡来人を専門に遺跡発掘調査・研究を行い、多くの功績を挙げ日本の考古学に貢献した。業績の中でも特筆すべきは、須恵器を倭国に伝えた渡来人が朝鮮半島南部の「馬韓(ばかん)」地域からも来ていたと1990年頃に発表し、それが認められて現在の定説となったことである。それ以前は朝鮮半島中南部の伽耶(かや)地域からのみ須恵器が伝わったとされていた。「それまでずっと学んできたこと、発掘してきた様々なことが一つ実を結んだかなと感じました」と酒井名誉教授は語る。

美濃焼で有名な岐阜県中津川出身の酒井名誉教授は、幼少期から陶磁器や骨董品に興味を持っていた。「中学時代は陶工になりたくて美大受験のために絵画の勉強をしていました」。転機は高校時代、小学生の頃から参加していた中津川考古学研究会の繋がりで、名古屋大学が実施する発掘現場へ行く機会を得た時だ。「その時に考古学への興味が再び頭をもたげて『古墳時代の須恵器という焼きものをもっと知りたい』と進路を決めたのです」。そして、駒澤大学の倉田芳郎先生が須恵器窯の発掘調査を行っていることを知り、駒澤大学文学部歴史学科を志望した。
入学後は倉田先生に師事し、群馬県の菅ノ沢窯跡で資料を見ながら発掘を行い、それが須恵器研究へと方向性を決定づけた。「考古学は遺跡や遺物により人類の過去を研究する学問」と教えてくれた倉田先生との忘れられないエピソードがある。「1年生のころに発掘した石積みの図面を一生懸命描いて倉田先生に見せた時のことです。私は自分なりにしっかり描いたつもりだったのですが、先生に『この図で本当にいいのか?間違っていると思うなら破れ』と言われてしまいました。その夜、図面を破って、もう一度しっかり観察して描き直しました。すると、中世の人たちが石を積み重ねた形跡まできちんと描くことができたのです」。その時、今でも大切にしている「『観る』ことの重要性」を認識したのだという。

駒澤大学大学院の修士課程を修了した後、千葉県や埼玉県で発掘調査を行い、窯跡や出土須恵器から当時の関東豪族たちの須恵器生産の導入や流通、大和王権との関わりなどを研究した。そして埼玉県で「古代の瓦から古代寺院を探る」という調査を任された。「瓦の文様から時代や系譜、仏教信仰の広がりまで研究の幅が広がっていきました」。さらに千葉県での発掘調査をきっかけに「渡来人」も研究対象になっていった。酒井名誉教授は「朝鮮半島百済で作られた土器を見つけましたが、それは朝鮮半島からきた渡来人が暮らしていたことを意味するのです」と語る。このように酒井名誉教授が研究してきた「須恵器」、「瓦」、「渡来人」が繋がり、関連づけられながら”考古学の新たな定説”を生み出してきたのである。
「駒澤大学はもう一人の恩師」と語る酒井名誉教授は、「学生には、何事においても特徴や違いを正確に『観る』目を養ってほしい。駒澤大学はそれを身に付けられる場所ですから」と話してくれた。

※ 本インタビューは『Link Vol.12』(2022年5月発行)に掲載しています。掲載内容は発行当時のものです。