白水 繁彦 名誉教授

目に映り、聞こえてくるものには”作者の意図”がある」。メディアリテラシーを高め、情報に操作されない人になろう。
移民研究の第一人者である白水名誉教授は移民のメディア文化論などにも知の領域を拡げ、さらにメディアリテラシーの重要性を説き民主主義社会を機能させるための提言を続ける。
白水名誉教授は現在、駒澤大学で「社会人ゼミ」と呼ばれる「グローバル・メディア・スタディーズ・ラボラトリ『社会とメディア』プロジェクト公開研究会」で講師を担っている。「これは私の理想のゼミ」と言う。なぜなら、参加者は年齢や学歴、職業など一切不問で「勉強したい人が勉強する場」だからだ。
ゼミの大テーマは「映像で学ぶ、映像を学ぶ」。白水名誉教授はテーマに即した映像作品を選択・提供し、必要であればゲスト講師を招き、映像鑑賞後に行われるディスカッションの舵取りをしている。学期毎のテーマは「日系移民の体験から民族・文化を考える」、「ドキュメンタリーの作られかた」、「戦争とプロパガンダ」などで、かなり踏み込んだ映像と課題を参加者に投げかける。しかし、ディスカッションは敷居が高いものではない。「参加者は自由に自分の意見を言い、質問します。こういう場はありそうだけど、なかなか見つからない。だからこのゼミを作りたかったわけです」。
もう一つ、ゼミで磨きたいと思っているのが〝メディアリテラシー〞である。「以前から、日本ではメディアリテラシーの教育が足りないと感じていました」。メディアリテラシーとは、メディアからの情報を批判的な思考も持って読み解くことができる力、そして的確に発信する力で、民主主義社会をより良く機能させるために必須の能力だ。「例えば、テレビで放映されるドキュメンタリーを鵜呑みにする人が多い。しかし、その映像作家が『なぜ、このシーンにこのアイテムをわざわざ写し込んでいるのか』を考える必要があります。なぜなら作家はそこに〝意図〞を持たせているから」と言い、「実は、私たちの目に映り、聞こえてくるものはすべて〝作者が作っている〞。作者が一流であればあるほど〝自然に〞仕込んできます」と続けた。「参加者がメディアや為政者に操作されることなく、自分で考えて行動、発言する民主主義の確かな担い手になる必要があると強く思います」。
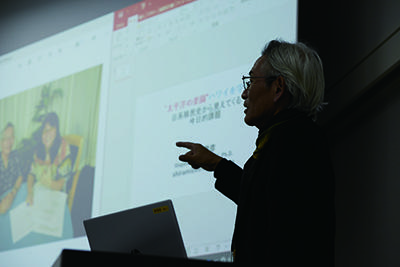
「ゼミを通して目指すのは〝ベターライフ〞。世の誰しもが将来に希望を持てる社会を作るにはどうすればいいのか、思考のきっかけを提供したいと考えています」。そして、ゼミは毎回、「ここで話し合った知見を、制度や教育をより良く変えるために、どう活用できるか考えてみましょう」という、白水名誉教授のメッセージで締めくくられる。
白水名誉教授の専門はメディア社会学、エスニック文化論など多彩だ。最初はマスコミュニケーションの研究をしながらアメリカでフィールドワークを行い、「小規模な地域メディア」に関心を持ち、ローカルメディアの研究を始めた。その後、移民の生活基盤である「エスニックコミュニティ」が存在することに気づき、エスニックメディアの研究へと広がる。特にハワイの日系人メディアや文化史については多数の著書があり、さらにハワイに暮らす沖縄系社会の研究から、海外沖縄系の文化についても多数の講演を行っている。
「私は海外で〝移民〞について、多角的に研究をしてきました。その知見を今、日本で暮らす外国人に対する法整備や教育問題の解決に活かせると考えています」と、提言を続けたいという思いも語ってくれた。

※ 本インタビューは『Link Vol.10』(2020年5月発行)に掲載しています。掲載内容は発行当時のものです。